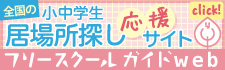PUBLICATION
出版
「居場所」難民 ―報道記者が見た不登校の深層―(四宮淳平・著)
「不登校を取材する記者」が「不登校の子を持つ親」としてたどり着いた令和型『子どもの未来のつくり方』
本書の内容
九州最大のブロック紙「西日本新聞」の教育担当編集委員として、長年、不登校現場を取材し続けた記者が、報道の枠を超え、不登校支援者となった。「報道だけでは変わらない」葛藤を抱きながら見つけた「報道でしか実現できない」可能性。自身の子どもが不登校となり、親として実感した当事者としての真実。長年の取材記録をもとに綴られる不登校の実態と「その後」。記者としてのキャリア、不登校の子を持つ親としての経験を糧に動き出したプロジェクトは、「報道することが具体的な課題解決につながる」という新しいジャーナリズムを生み出した。なぜ、子どもたちには「居場所」が必要なのか。本当の課題はどこにあるのか。「自分には何もできない」と思っていても、必ず一人ひとりに「役割」があると気づける一冊。どんな小さなことからでも始められる、令和型「子どもの未来のつくり方」。
◎本書のポイント
・長年の取材をもとに書かれた報道記者による不登校の実態
・不登校の子どもの親として実感した「不登校支援」の現実
・フリースクールなど多様な居場所の必要性と課題
・課題解決に向けた具体的な行動
・誰もが「小さなこと」から始められる不登校支援
目次
はじめに
第1章 新聞が報じない不登校の「その後」
今も残るいじめの傷(サキさん)/どこかで適切な支援があれば/耐えがたい教室(ヒカルさん)/「自分はどうして生まれてきたんだ!」/苦しむ母親たち/「ワンオペ育児」からの不登校/人生は誰のもの?/地下鉄でも見える母親の重圧
第2章 わが子の不登校で見えた現実
起きない子 ざわつく心/心の中は「出席」、言葉では「欠席」/「不登校を受け入れる」 当事者になって分かった理想と現実/「不健康」を受け入れる/「炭鉱のカナリア」 中学生の10人に1人が不登校傾向
第3章 学校現場の「姿」
順番待ちから一転、なり手不足に/「荒れ」はなくても画一化/学校に「スタンダード」が生まれる背景/主体性を阻む壁/「新人の力は落ちている」/採用後1年未満の退職教員は過去最多/「おまえらは、くずだ」/問うべきは公教育の在り方
第4章 フリースクールの可能性と課題
フリースクールで自信/月10万円の費用負担/学校外の選択を「普通」に/日本社会の問題を学校外から解決/フリースクールに行かない/フリースクール経営の難しさ
第5章 報道するだけでいいのか
新聞記者としてのジレンマ/なぜ報道するのか/報道しても不登校は減らない/感じた限界 支援者になろうと大学院へ記者だからこそ、できること/数十秒で考えたアイデア/クラウドファンディング 記者としての総力を投じ寄付集め/「新聞社がなぜ、資金集めをするのか」 公的機関としての批判/フリースクール利用費を補助 基金の創設/「生きる意味」をつくる/動き出した支援/「困っていること」を持ち寄る 多様な大人たちの「地域円卓会議」
第6章 私たちにできる不登校支援
「私、本当は行きたくなかった」/保護者支援がつなげた子どもの未来/「学校に戻す方法は分かりません。ただ…」/私たち「大人」にできること/三つの具体策
おわりに
著者プロフィール
四宮淳平(しのみや・じゅんぺい)
1980年、徳島県生まれ。2005年に九州大学工学部を卒業し、西日本新聞社に入社。福岡市や福岡県の行政や政治、地域情報などを担当。2010年から4年間は長崎県諫早市に拠点を置く支局に勤務した。その後は福岡市の本社に再び異動し、2020年から教育分野の報道を担当する編集委員。同年から2年間は事業構想大学院大学の福岡校で研究し、事業構想修士の学位を得た。その研究成果を生かし、不登校支援を目的とした2回のクラウドファンディングに携わるなどしている。
読者の皆様からのご感想
行間にあふれる著者の汗と希望。
そして社会の矛盾に対する憤り。
四宮著者の取材力と行動力に拍手を送り続ける一人です。
(福岡県・男性)
| ■ 著者: | 四宮淳平(西日本新聞 編集委員) |
| ■ 発行: | 学びリンク |
| ■ 定価: | 1,760円(税込) |
| ■ ISBN: | 978-4-908555-82-4 |
| ■ 体裁: | 四六版156ページ |
| ■ 発売日: | 2025年8月20日 |